10年以上農業系のサラリーマンをしている「いのっぷ」です。家では娘をなんとか子育てしています。
ここでは初心者でも分かりやすいように家庭菜園の始め方を簡単に説明しています。
家庭菜園に興味を持って調べても「○○農法」「有機栽培」などが出てくると「何か難しそうだなぁ。」と思ってしまいますが、初心者が趣味としてやるのなら↓のことだけできれば大丈夫。
- 土地を決める(プランターOK)
- 必要な道具を揃える
- 失敗しやすいポイントをおさえる
- 作りやすい野菜を選ぶ
順を追ってやれば良いようにステップ形式で解説していきます。
普段、畑で作業をしていて初心者が失敗しやすいと思うポイントは詳しく解説するので、それを抑えるだけでも上手くいくと思います。
(これでも難しいなと思う人は、初めは試しに土地、道具、野菜の種苗、作業アドバイザー全てが揃っているレンタル農園を利用する方法もあります。)
また、出掛けずに子供ともできる家庭菜園は子育て中にオススメな趣味です。
子育てをしているとなかなか遊びに行けず、自分の時間があまり取れません。子育てにしっかり向き合っている人ほど妻(夫)や子供に気を使って外出したり、趣味の時間を持つのを我慢しているのではないかと思います。
しかし、子育てをしている経験としてひと息つける時間を作るのはとても大事です。家庭菜園であれば家で子供ともできるので気を使う必要はありません。
野菜作りに触れたことが無いひとは難しく感じるかもしれませんが、ポイントをおさえて少しずつやれば大丈夫。
私も娘と家庭菜園をしているので、一緒に始めてみませんか?
家庭菜園の簡単な始め方[6STEP]
全く野菜作りにふれたことが無い人が1から始める具体的な方法を6STEPで解説します。
この通りにやれば始められるように細かく説明するので家庭菜園に挑戦しようか迷っている人は読んでみてください。
[STEP1]畑を決める(プランター、庭、市民農園、レンタル農園)
まずは畑を決めます。一般的には以下の中から選ぶことになります。
- プランター
- 自分の庭
- 市民農園
- 民間レンタル農園
プランター
家庭菜園に興味はあるけど自分にできるか不安という人や続けられるか分からないという人にオススメです。
自分の庭が無い人や土地があっても土が野菜を育てられる状態ではないという人にも向いています。
肥料入りの培養土を使用すれば、苗を植えるだけで始められて失敗しにくいので試しにやってみるには良いと思います。
注意点は小さいプランターを選びがちなので、大きめのプランターを選びましょう。
こんなに大きなプランターを置けない場合は小さいプランターでもできる小松菜、ホウレンソウ、ベビーリーフなど小型の葉菜を育ててみるのが良いですね。
自分の庭
自分の庭があれば家庭菜園スペースを作るのがオススメです。子育て中であまり出かけられない人や子供と一緒にやりたい人には特に。畑へ通う手間も無いし、他人を気にしなくて良いですし。
家族で庭から採った野菜を料理して食べるなんて良いですよね。
注意点は野菜を栽培できる土では無いかもしれないことです。
住宅地には真砂土を入れていることがありますが、この土は肥料の持ちが悪く、雨が降るとべちゃべちゃになるので栽培に向きません。その他の土でも造成に使われる土では野菜の栽培は難しいです。
オススメは家庭菜園エリアの土を黒土に入れかえることです。
ただ、土の入れ替えは自分でやると大変なので「レイズドベッド」を設置してみると良いと思います。
レイズドベッドは簡単に説明すると枠で囲って、その中に植物の栽培に向く土や堆肥を入れるやり方です。花壇をイメージすると分かりやすいです。
土を入れ替えるより硬い土を掘り返す必要がないので負担が少ないです。
市民農園
プランターや庭の小さい畑では物足りないという人には市民農園がオススメです。
民間の貸し農園に比べると費用が安いので予算的には始めやすいです。(年間で1万円以下)
申し込みできる時期が決まっている自治体もあるので、興味がある人は早めに調べましょう。
基本的には畑を借りるだけなので、道具や種、苗は自分で揃えなくてはいけません。また、トイレ等の設備は整備されていないことが多いです。
栽培方法を相談できる人もいないので、野菜を育てるのが初めての人はまずプランターや自庭で小さく始めるか、サポート付きの貸し農園がオススメです。
民間レンタル農園
レンタル農園では自治体が管理している市民農園とは違い設備や栽培サポートが充実しています。道具や肥料、種苗も用意してくれているので手ぶらで行くだけで野菜を栽培できます。
(PR)手ぶらで行けるサポート付き貸し農園【シェア畑】(シェア畑HPへ移動します。)
家庭菜園に興味はあるけど続けられるか分からないという人にはオススメです。道具や肥料などを揃えるのが一つ目の壁になっていると思います。
続けるか分からないのにクワやスコップを買い揃えるかは悩みますよね。
また、マルチや肥料は使い切れず余るので保管スペースにも困るかもしれません。どうしても農具は汚れますしね。
民間の貸し農園は月1万円ほどかかるので料金は高いですが、道具などを買う費用がかからないので単年でみると市民農園でやる場合との差は小さいかと思います。
始めに良い体験をするのは続けていく上で重要ですよね。
一度教えてもらいながらやってみると作業の流れが分かるので、市民農園などを利用する場合もやりやすくなります。
畑選びについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を読んで下さい。
[STEP2]必要な道具を揃える
土地が決まったら次は道具を揃えましょう。
まずは必須なもの
- クワ
- 先が尖った剣先スコップ
- 小さいハンドスコップ
- メジャー
- ヒモ
- 手袋、長靴、帽子
- 板(15cm×80cmくらいの大きさ)
- 肥料
庭で2坪ほどの小さな家庭菜園(例として2m×3.3m)をする場合は↑の物があれば始められます。(プランターで植える場合は肥料入りの土があればOK)
クワ
「平クワ」という畝やベッドを作るのに適したものを買いましょう。
スコップ
畑を耕すのが主目的なので先が尖った剣先スコップがオススメです。小さいハンドスコップは苗を植えるときや細かな作業をするときに便利です。
メジャーとヒモ
株間、畝間を測って適切な間隔で植えてあげるのは野菜の生育に重要です。
ベッドを作るときにヒモを張って真っすぐできると初心者っぽさがなくなります。庭でやるなら見た目もキレイにしたいですよね。
手袋、長靴、帽子
身に着けるものも忘れずに用意したいです。手を怪我したり、靴がドロドロになったり、熱中症になったりすると家庭菜園が嫌になるかもしれませんね。
板
意外と便利です。ベッドの上をならして、押し固めるのに使います。10cm毎に印をしておけばものさし代わりにも使えます。
肥料
化成肥料と有機肥料がありますが、こだわらないのであれば化成肥料がオススメです。成分量がはっきりしているので扱いやすいです。
さらに規模を大きくしたり、野菜ごとに必要ならば
- マルチ
- マルチストッパー
- 田引(たびき)
- レーキ
- 草削り
- 防虫ネット
- ダンポール
- 支柱
- 誘引するバンドや麻ひも
- 農薬
マルチとマルチストッパー
マルチは地面を覆うことで以下の効果があります。
- 保温
- 乾燥防止
- 肥料成分の保持
- 泥はねを抑えて病気予防
- 雑草抑制(透明マルチ以外)
マルチには「透明」「シルバー」など色々な種類がありますが、初めての人は「黒マルチ」を使いましょう。一般的なので、どこのホームセンターでも売ってますし価格も安いです。
黒色だと日光を遮って高温になり過ぎる失敗をしにくく、雑草を抑制できるので週末しか手をかけられない人にはオススメです。
マルチを張るなんて大変そうだと思うかもしれませんが、意外と簡単です。やり方は解説するので挑戦してみてください。
「マルチストッパー」はマルチを抑えるのに使います。
マルチはピンッと張ってあげると風であおられず、剥がれにくくなります。また、地面に密着していると保温、保湿性を発揮できます。
田引(たびき)
ヒモを張る道具です。小さな家庭菜園ではビニール紐で充分ですが、市民農園を借りたりして面積が広くなったら用意しましょう。
レーキ
ベッド上を慣らしたり、石や土の塊を掻き出すために使います。小面積では板で代用できましたが、面積が広くなると大変なのでレーキを用意しましょう。
ベッド上を真ん中が少し高くなるように慣らしてあげれば、水が溜まりづらくなり失敗を防げます。また、播種する場合は表面を均一な状態にすることで発芽を揃えられます。
「アメリカンレーキ」という物もありますが、ベッド上を慣らすには使いづらいので注意しましょう。
草削り
除草用や簡単な土寄せができる道具です。ネットでは「草削り」で出てきます。
畑が広くなると手で抜くのは大変なので、立ったまま使える草削りを用意しましょう。
草を抜くのではなく、地表面をまんべんなく削るように使います。
防虫ネットとダンポール
葉菜(小松菜、キャベツなど)を栽培する場合は防虫ネットを使用しましょう。農薬を使いたくない人は必須です。
「ダンポール」はトンネルの骨組みになる資材で、軽くて柔らかいので扱いやすいです。地面への差し具合でトンネル幅や高さを調整できるので、ベッドの寸法を変えても使えるので便利です。ガラスファイバーなので素手で作業するとチクチクするので手袋をしましょう。
支柱と麻ひも
果菜(トマト、ナスなど)を栽培する場合は支柱と誘引する麻ひもを用意しましょう。
支柱に誘引して上に伸ばしてあげて、実が地面につかないようにしましょう。スペース的にも効率良く栽培できますね。
麻ひも以外にも簡単に誘引できるバンドなどもあります。
農薬
家庭菜園では無農薬で栽培したい人が多いと思いますが、使用した方が成功する可能性はあがります。
大きく分けると「虫害を防ぐ殺虫剤」と「病気を防ぐ殺菌剤」があります。家で食べるだけならば多少病気がでても問題ないので殺菌剤は使わなくても良いかなと思いますが、虫が多発すると食べられてしまうので殺虫剤は使用した方が栽培しやすいです。
農薬を使用しない場合は防虫ネットで覆ってあげて虫害を防ぎましょう。
家庭菜園の道具について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を読んで下さい。
[STEP3]栽培前の準備(土作り、肥料入れ、耕す、マルチをはる、、、など)
土作り
野菜の栽培には適した土作りが必要で、宅地造成に使われる真砂土などは向いていません。初心者には土壌改良は難しいため、土の入れ替えがオススメです。具体的には家庭菜園にする場所の土を掘り出し「黒土」を入れます。
掘り出した土の処理にはコストがかかるため、同量の黒土と混ぜて畑に戻す方法もあります。その場合は土量が増えるので、レンガや土止めなどで囲ってレイズドベッド(花壇のようなもの)にして土を入れます。
固い地面を掘り起こすのは大変なので、2坪(6.6㎡)以下の小さい家庭菜園にするのがオススメです。
土作りの手間を省きたい場合はプランターを使用します。その場合は培養土を購入するだけで始められます。
ウチは外構工事のときにレンガで囲って、土の入れ替えをやってもらいました。家を建てるときに家庭菜園をやると決めているならばプロにお願いするのがオススメです。
肥料入れ
土の用意ができたら次は肥料を入れてあげます。
入れる肥料は大きく分けて3つです。
- 堆肥
- 石灰(ph調整)
- 三要素肥料(チッソ、リン酸、カリウム)
堆肥は「牛ふん堆肥」を使う
肥料の効果がある堆肥は家畜のふんとワラを混ぜて発酵させた堆肥です。
色々な種類がありますが、初心者は「牛ふん堆肥」を使いましょう。入れる量は2~3kg/㎡(5~7.5ℓ/㎡)。家庭菜園を始めたばかりの畑はこの範囲で多めに入れます。
牛ふん堆肥は効果が緩やかに出るため失敗が少なく、肥料成分が長期間にわたって効くため、野菜を栽培しやすい畑になります。
堆肥は苗を植え付ける一か月前に入れます。少し臭いが気になるかもしれないので、堆肥をまいたらすぐに耕してあげましょう。
「牛ふん」というと抵抗があるかもしれないけど、売っているものは発酵して原型はないので大丈夫ですよ。
石灰は「苦土石灰」を使う
石灰は畑を野菜の栽培に適した弱酸性pH6~6.5(中性が7.0)に調整するために入れるカルシウム肥料です。
初心者は粒状の「苦土石灰」を使いましょう。入れる量は100~200g/㎡程度です。
苦土石灰はアルカリ性の強さが中程度で失敗しにくいです。ゆっくり溶けるのでチッソ肥料と一緒に撒けますし、水を含んでも発熱しないので苗をすぐ植えられます。
肥料成分としても苦土(=マグネシウム)、石灰(=カルシウム)は葉が大きく成長するキャベツなどの葉菜では多く必要となります。
粒状の製品は扱いやすいので撒きムラがでにくく、粉状より粒が大きくじわじわ溶けるため効き方が穏やかです。
三要素肥料は「化成肥料」を使う
三要素とは野菜栽培で必要な「チッソ、リン酸、カリウム」です。
- チッソ・・・葉肥
- リン酸・・・実肥
- カリウム・・・根肥
と言いますね。
大きく分けると2種類あり「化成肥料」と「有機肥料」があります。
その中でも初心者は「化成肥料」がオススメです。
化成肥料の成分量は商品により色々あるのですが、「8-8-8」はホームセンターなどで良く置いてあります。
この意味は「チッソ:リン酸:カリウム=8%:8%:8%」の割合で含まれているという意味です。なので化成8-8-8を1kg施用するとチッソ:リン酸:カリウムを80g:80g:80gを入れられるという事です。
以下が投入量の目安になります。
葉根菜類(キャベツ、ダイコン、コマツナなど)は
「チッソ成分量20g/㎡を目安に化成8-8-8の場合250g/㎡」
果菜類(トマト、ナス、キュウリなど)は
「チッソ成分量15g/㎡を目安に化成8-8-8の場合190g/㎡」
ナスはそれに株あたり一握り、キュウリ、カボチャなどウリ科は二握りを植える所にまんべんなく撒いてください。トマトはそのままでOK。
(化成肥料の一握りはおおよそ30~40g。心配ならば自分の一握りを測っておくと便利)
縦2m×横1mであれば2㎡ですね。多少違っても問題ないので、おおざっぱにキリが良い数字で測りましょう。
本を参考にして肥料を正確に入れようとするとトマトは何g、ナスは何g、キュウリは何gと細かく分かれてしまいます。マジメに施肥量を品目ごとに変えようと思うと大変なので、ここで挙げた量を撒いてください。それぞれの品目に最適量ではないかもしれませんが、家庭菜園としては問題ありません。
先に大まかに肥料を入れるメリットとして、スケジュールが楽になります。事前に植える野菜を決める必要がないので、植えるときにホームセンターへ行って苗を見ながら選べます。
子供と一緒に何を植えようか話しながら決めると楽しいですね。子供も自分で選んだ野菜を植えられると嬉しいと思います。
耕す
堆肥や肥料を撒いたら良く耕します。耕すことで以下の効果があります。
- 肥料を均一に混ぜ合わせる。
- 固まった土を砕いて、土壌の通気性、水はけを良くする。
- 空気を入れること微生物が活性化して有機物の分解が進む。
微生物が堆肥を分解する過程で腐植が生成され、これが土壌の通気性、保水性、保肥力が優れる団粒構造を形成し、野菜の栽培に適した状態にします。
家庭菜園での耕す方法は初心者にも扱いやすいスコップがおすすめです。畑の端からスコップで土を均一にひっくり返すようにして耕します。
畝立て、ベッド作り
野菜は通気性が良い土壌を好むため、耕した後は畝やベッドを作ります。高さ約10~15cmを目安に高めの畝を作ることが有効です。雨水が溜まったときでも畝は水に浸からず、早く乾くため、根腐れを防げます。
高畝にすると乾燥し過ぎるデメリットがありますが、家庭菜園の規模ならば水やりも簡単なので問題ありません。
畝を立てる手順は↓の通りです。
- 畝やベッドの寸法をメジャーで測る。
- 畝の両端にヒモを張る。
- ヒモにそって平クワで土を盛りながら溝を掘る。
- ベッドは慣らしてから上と側面を押さえて鎮圧する。
畝幅は一列植えの畝だと50cm、2列以上植えるベッドだと80~100cm。
畝の両サイドに端から端までヒモを張ります。小さい家庭菜園であれば適当な棒にビニール紐を結んであげれば大丈夫です。
クワは「平クワ」を使い、張ったヒモにそって溝を切っていきます。高畝にするので土は畝にする側に盛りましょう。
溝が切れたらベッドの上を平らにならします。そして、ベッドが崩れないように上部と側面を押さえて鎮圧します。小さい面積なら適当な板で抑えてあげれば充分です。
マルチ張り
ベッドにした場合はマルチを張るのがオススメです。意外と簡単に張れますし、栽培しやすくなりますよ。
マルチのサイズはベッド幅+50cm程度(ベッド80cmなら130cm)の物を使いましょう。大きめのマルチを使うと、土を被せて抑えるのが簡単です。
マルチ張りは2人居るとやりやすいです。ベッドの端で押さえてもらい、両端から強く引っ張って、四隅をマルチストッパーで固定してから土を被せていきます。ベッドの両端を土で押さえ、二人で両サイドから引っ張りながら横にも張りながら土で押さえます。
これで完了です。意外とやってみると簡単ですよ。
ここまでの作業ができれば植える前の準備は完了です。
栽培前にする畑の準備について詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。写真付きで分かりやすく解説しています。
[STEP4]種まき、苗を植える
オススメする野菜の組み合わせは↓のとおり。(寒い地域は例外)
春に果菜類(トマト、ナス、キュウリなど)
秋冬に葉根菜類を栽培(キャベツ、ハクサイ、コマツナ、ダイコンなど)
これらの野菜は旬の時期で栽培しやすく、家庭菜園の初心者でも挑戦しやすいです。
初心者は種まきから始めるより、苗を買うのがオススメです。(コマツナ、ダイコンなどは種で播きます。)
苗を植えるポイントは↓のとおり。
- 株間を測る。
- 千鳥で植える。(2列で植える場合)
- 株元をしっかり押さえる。
- 水をたっぷりあげる。
- 適期に植える。(果菜類はゴールデンウイークくらいに)
株間を測る
株間をしっかり測って植えましょう。苗ラベルの説明通りに株間をとることで、適切に生育させられます。窮屈に植えてしまうと日当たり、風通しが悪くなり、生育不良や病気の原因になります。
株間の目安は↓のとおり
果菜類・・・50cm
葉菜類・・・40cm
購入した苗のラベルの通りに植えればOKですが、よく分からない場合はこれで植えれば大丈夫です。
千鳥で植える
千鳥植えとはジグザグに植えるということです。2列で植える場合に横並びで植えるよりも、ジグザグで植えた方が日当たり、風邪通しが良くなります。
株元をしっかり押さえる
植えたときに株元をしっかり押さえましょう。苗の根鉢を地面にしっかり密着させることで根着きが良くなります。
水をたっぷりあげる
植えた後はしっかり水をあげます。果菜のポット苗は植穴に水を入れてから植えると良いです。
適期に植える。(果菜類はゴールデンウイークくらいに)
苗は適期に植えます。販売している種や苗には植える時期がラベルに書いているので、それを守って植えましょう。
春に果菜類を植える場合、定植適期の後半が特にオススメです。早春は遅霜がおりる可能性があります。関東~関西であればゴールデンウイークくらいに植えるのが失敗しにくいです。
コマツナ、ホウレンソウなどの小型の葉菜やニンジン、ダイコンなどの根菜は種を播いて栽培します。種まきをする場合は多めに播いて、良い株だけに間引くのがコツです。
[STEP5]管理、観察をする
植えた後も適切に管理をしてあげます。家庭菜園なのでよく観察して日々の変化を感じるのも楽しみですね。子供は植わっている野菜に触れる機会が少ないので喜んでくれると思います。
娘が「キャベツだー!」って喜んでいるのを見たとき、家庭菜園やって良かったなと思いました。
葉根菜では植えた後すぐに防虫ネットをかけます。葉物野菜は虫に食われやすいので虫への対策は必須です。農薬を使えばよいのですが、家庭菜園では抵抗感がある人が多いと思います。葉根菜は防虫ネットをかければ、その後の管理はほとんど無いので楽です。
果菜類では支柱を立てて誘引します。主茎を麻ひもで8の字になるように支柱に縛ります。茎を傷めない程度にしっかり縛りましょう。随時、頭が下がってきたら誘引してあげます。
また、脇芽とりをします。茎から葉がでている部分から脇芽が発生するので、定期的に取り除いてあげます。放置すると脇枝が伸びてジャングル状態になってしまいます。養分が分散してしまい、良い実が取れないので注意しましょう。
果菜類の管理は職人の世界で、調べれば難しい方法がたくさん見つかるのですが、初めて家庭菜園をするのであれば簡単な誘引と脇芽とりだけ気をつければ問題無いです。
あとは生育の状況を見て、追肥をしてあげます。
葉根菜では結球するキャベツ、ハクサイは植えて2~3週間後に、ダイコン、ニンジンは間引きの後に化成肥料(元肥と同じでOK)を一つまみずつ株元にあげます。小型の葉菜は追肥の必要がありません。
果菜類は実がなり始めたら7~10日くらいに一度のペースで液肥をあげます。
以上が大体の管理作業です。こだわればいくらでも作業はあるのですが、初めての家庭菜園なので充分です。どうせなら色んな野菜を植えたいと思うので、簡単な管理でやりましょう。
家庭菜園の醍醐味は観察するところにあると思います。
収穫された野菜はスーパーに行けば見られますが、苗の姿やそこからどんな風に成長して収穫できる野菜になっているのかは家庭菜園で育ててみないと見られませんからね。
野菜がどんなふうに育っているか、農作業がどれだけ大変かを知るのは、子供にとって大事な事だと思います。「食べ物」はみんなに関係することで、将来的な課題になると思いますからね。
[STEP6]収穫をする
とうとう収穫です。
初めての家庭菜園で無事に収穫できたら嬉しいですよ。
寒い時期だと畑にしばらく収穫せずにおいておけますが、最高気温で20℃くらいある時期は育ち過ぎるので、なるべく早く収穫しましょう。慣れてくれば早くできる品種と遅くできる品種を植えて収穫をずらすこともできます。
果菜類は実を採らないと樹が弱るので、しっかり収穫します。(もったいないですが、食べられなくても採りましょう)
同じ野菜をいっぱい植えると食べるのが大変になるので、少しずつ色んな野菜を植えるのがオススメです。
初心者が家庭菜園で失敗しやすい11のポイントと解決方法
家庭菜園の始め方を解説してきましたが、その中でも普段農業をして色々な人の畑を見ていると失敗するポイントは大体同じです。特に未経験の人が引っ掛かりやすいポイントは↓です。
- 野菜を育てられる土でない
- 排水ができていない
- 日当たりが悪い
- マルチを使わない
- 虫の対策をしない
- 栽培する時期が合っていない
- 窮屈に植えすぎる
- 粉状の肥料を使う
- 化学肥料を使わない
- 種まき、育苗をする
- 規模を広げ過ぎる
- 難しい野菜に挑戦する
①野菜を育てられる土でない
土地の造成工事に使われる真砂土は排水性が悪く、肥料を保持する力が弱いので植物を育てるのには向いていません。土壌改良か土の入れ替えが必要です。
それが大変な人はプランターでの栽培がオススメです。肥料も入っている野菜用培養土を使えば植えるだけでOK。畑で栽培したい場合はレンタル農園や市民農園を借りる方法もあります。
ウチは家庭菜園の土を栽培に向いている黒土に入れ替えてもらいました。
②水はけが悪い
やや乾燥している土壌が好きな野菜が多いので、畑の中に水が溜まらないようにしてください。過湿状態になると根が酸欠で腐ってしまいます。
畑の外に向けて少し傾斜をつけるか、溝を掘ってあげると良いです。
難しければ畝を高めにしてあげると湿害は抑えられます。(乾きやすくなるので水やりに注意)
水はけ対策は忘れがちですが、プロの農家さんでも「何か出来が悪いんだよね」っと言うときは水が溜まりやすい圃場だったりすることは多いです、、、
③日当たりが悪い
野菜は光合成するので、お日様に当たらないと良くできないです。
分かっていても日当たりは土地の都合なので改善が難しいところでもあります。
対策としてはプランターを使って午前中だけでも日当たりが良い場所で栽培することです。プランターでも大きいサイズで土量をしっかり確保すれば良くできます。
④マルチを使わない
マルチとは地面を覆うポリエチレンフィルムで黒や透明、シルバーなど用途にあわせて色々な種類があります。地温を高めたり、乾燥を防いだり、たくさんの効果があります。
初心者は黒マルチがオススメ。
理由は
- 草を抑えられる
- 安い
- 手に入れやすい
家庭菜園初心者だとマルチを張るのは大変だと思うかもしれません。
しかし、やってみると簡単に張れますし、マルチを使わずに露地で栽培する方が難しいです。
⑤虫の対策をしない
野菜の品目によりますが虫の対策は必要です。プロの農家でも虫の防除に苦労しています。
用法、用量を守って農薬を散布するのがオススメですが、家庭菜園で農薬は使いたくないという人も多いと思います。
そんな人は防虫ネットでトンネルをしてあげましょう。
これだけで虫の対策をしないよりも格段に成功率があがります。
⑥栽培する時期を間違っている
種まきや植える時期を間違えると失敗します。
ネットや本を見れば野菜毎に大体の時期は分かるんですが、初心者の人が戸惑いやすいのは
自分の畑はどの地域区分になるの?
という点です。
おおよその分け方で冷涼地、中間地、温暖地になっており、それぞれに栽培時期が書いてあります。自分の地域区分が分からないと、どれを見たら良いか分からないです。
一番簡単な対策は苗で買うことです。
お店はそのときに植えられる苗を仕入れるので、買ってきてすぐに植えれば時期を外すことはありません。
⑦窮屈に植えすぎる
野菜には適正な栽植密度があるので、適度な間隔を空けて植えてあげましょう。
過密だと
- 葉を広げるスペースが無く充分に生育できない
- 日当たりが悪く生育不良になる
- 風通しが悪いので蒸れて病虫害の原因になる
自分で家庭菜園をしてみると、狭い畑に色んな種類の野菜を植えたくなりますね。
⑧粉状の肥料を使う
粉状の肥料は均一に撒きづらく、扱いが難しいです。
風に舞って目や口に入って嫌な思いをするかもしれませんし、子供と一緒だとなおさら避けたいですね。
粒状の肥料が使いやすいのでオススメです。
⑨化学肥料を使わない
なんとなく化学肥料に悪いイメージを持っていて家庭菜園では使いたくないかもしれませんが、肥料の3要素「チッソ、リン酸、カリウム」の成分量が分かりやすいので初心者の人にはオススメです。
有機肥料は肥料成分の含有量が分かりづらく、溶け出し方も肥料によって異なるので慣れない人には難しいと思います。(牛糞堆肥はゆっくり効いてくるが、鶏糞堆肥は早く効くみたいな感じ)
肥料の入れ方は土の状態次第なところもあるので「肥料成分をどれだけ入れて、自分の畑でどんな生育になったか」を把握するのはレベルアップしていくには重要です。
⑩育苗をする
種を播いて苗を育てるのは難しいです。初心者の人は苗を買ってくるのがオススメです。
発芽させるにはコツがあり野菜毎に適正な温度にしたり、光の好き嫌いがあったり。
育苗期間中は毎日水をやらないといけないし、夏場は日中に乾いてしまうので仕事をしていると難しいですね。
会社で育苗をしていますが、夏場に良い苗をつくるには朝、夕の管理だけでは難しいです。
苗を買うメリットは上の方でも書きましたが、時期を間違えにくい点もあります。植えたい日に買ってきて植えられるのはラクですね。種を播くなら逆算して計画的に播いておかないと定植が遅れて失敗します。
⑪規模を広げ過ぎる
広い場所を借りられたからと言って規模を広げ過ぎると失敗します。というか嫌になるかもしれません。
植えるときはテンションが上がっているので頑張れるんだけど、野菜作りは継続して管理していかなくてはなりません。
特に草は場所が広いほど生えてくるので、終わりない草とりに嫌になってしまいます。
それで止めてしまうのはもったいないので、一度小さい面積で始めて自分が管理できる量が分かってから増やすのがオススメです。。
野菜作りは虫、草との闘いです!
⑫難しい野菜に挑戦する
始めは手間がかからず、特別な栽培管理が必要ない野菜がオススメです。
葉菜
- コマツナ
- チンゲン菜
- ホウレンソウ
これらは小型で、生育期間が短いので栽培が簡単です。
マルチをかける必要もなく、直播をして発芽すれば防虫トンネルをかけておけば、収穫できます。
根菜
- ミニダイコン
これもコマツナなどと同様に、直播をしてトンネルをかけておけばOKです。
種を多めに播いて、間引きをするのがコツです。
通常のダイコンより根長が短いので、深く起こせていなくても失敗しにくいです。
果菜
- ミニトマト
- ナス
- ピーマン
果菜はプランターでの栽培がしやすいので、土作りの手間が無いのがメリットです。
50ℓ容量の大きいプランターに培養土を入れてあげれば、あとは購入した苗を定植すれば完了。
枝の管理など奥が深いですが、難しいことをしなくても、収穫はできます。
初心者が家庭菜園で失敗しやすいポイントのまとめ
野菜作りに慣れていない人が失敗しやすいポイントを挙げました。これらを注意すれば「全く収穫できなかった。」とか「大変過ぎて嫌になった。」という事にはならないです。初挑戦で嫌になって家庭菜園をやめてしまうのはもったいないので、ここで挙げたポイントをおさえてやってみてください。
失敗ポイントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事でさらに詳しく書いてあります。
「家庭菜園は難しい。。。」初心者が失敗する12個のポイントと簡単な解決方法
ただ考え方にはなりますが、家庭菜園なので必ずしも良い野菜が収穫できなくても、屋外で農作業を楽しんだり、野菜の生長を観察して小さな変化に喜びがあれば良いと思っています。
子供と家庭菜園をやるのであれば楽しめればOKですよね。一緒に汗をかくのは思い出になりますよ。
子育て中の趣味に家庭菜園がオススメな理由
私が経験から子育て中の趣味に家庭菜園を勧める理由は以下の通りです。
子育てをしているとあまり遊びに行けない
「子供が生まれてから付き合いが悪くなった」なんて良く聞きますよね。
実際に子育てしていると忙しいのと、体力的にキツイので遊びに行く余裕がありません。
しかし、何より妻も疲れているし、子供が一緒に居たがっているのに自分だけで遊びに行くのは申し訳ないという気持ちでした。
ただ、たまには好きな事をしたり、友達と話したり、ボーっとする時間は必要です。
育児は長期戦なので我慢し過ぎると、
些細なことで子供を強く叱って、我に返って自己嫌悪
のような悪いサイクルになってしまいます。
そんなときは少し自分の時間が取れるだけで、頭がスッキリしました。
家でもできるから出かけなくて良い
家庭菜園は庭があれば家でできますし、アパートでもベランダにプランターを置いてできるので出かける必要がありません。
そのため、家族に気を使うことも無いし、ちょっとした隙間時間で植物の世話をしたり様子を見てあげられます。家の中では息が詰まるので、外に出て日に当たると気分が変わりますよ。
野菜作りが日常のちょっとした楽しみになって、子育てから少しでも頭が離れる時間が作れると良いですね。
子供と一緒にできるし、教育に良い
子育てから離れることを言いましたが、家庭菜園は子供と一緒にできる趣味にもなります。子供って土いじり好きですよね。
最近は小さい子供でもテレビやスマホばっかりになりがちなので、外で遊ぶ機会を作ってあげられるのも良いですね。
野菜に興味を持って食べることにも挑戦してくれると言うことありませんが、そこまでは期待し過ぎですかね。
妻(夫)も休める
私が子供と一緒に家庭菜園をしているときは、妻が一人の時間を作れます。
パパがママに喜ばれる方法は子供と二人で遊んだり、出かけることだと思っています。
夫婦で協力してお互い一人になれる時間を作れると少し楽になりますね。
小さい子供と外出するのはとても大変なので、街中に出かけなくていい家庭菜園はちょうど良いです。
お金がかからない
子育てはお金がかかります。育児中でもかかるし、将来の教育費なども貯めなくてはなりません。
家庭菜園はお金がかからないので、一人暮らしのときから激減したお小遣いでもできる数少ない趣味です。
子供と一緒にできたり、食費の足しになれば、道具を買うのに少しお金がかかっても許してくれるかもしれませんね。
最近は特に物価が高くて趣味にお金を使う余裕がありません。
家族で共有できる
野菜が採れたら家に持ち帰ってみんなで食べられます。
そうすれば一緒に家庭菜園をしてなかった妻とも共有できます。
私の娘も「自分が育てたナスだよ。」って妻に自慢してました。
外に遊びに行くと妻は私と子供が何をしていたのか分からないけど、野菜を持って帰って「水やったよ!」とか「収穫したよ!」って話ができれば、一緒に楽しめますね。
子育て中の趣味に家庭菜園をオススメする理由は以下の記事で詳しく書いています。
「育児中は趣味をあきらめた。。。」→パパ、ママには手軽な家庭菜園がオススメ
いのっぷ家庭菜園の観察日記
家を建てたので私も家庭菜園やガーデニング(花は素人ですが)を始めました。
家庭菜園に興味を持った方は見てもらえると嬉しいです。
まとめ
野菜づくりが初めての人でも家庭菜園を始められる方法をまとめました。
野菜ごとに適切な管理がありますが、家庭菜園であれば気楽に始めたら良いです。うまく野菜ができなかったとしても、野菜の成長を子供と観察できれば趣味としては成功です。
特に、子育て中の人にはオススメの趣味です。
小さい規模からでいいので家庭菜園を始めてみましょう。
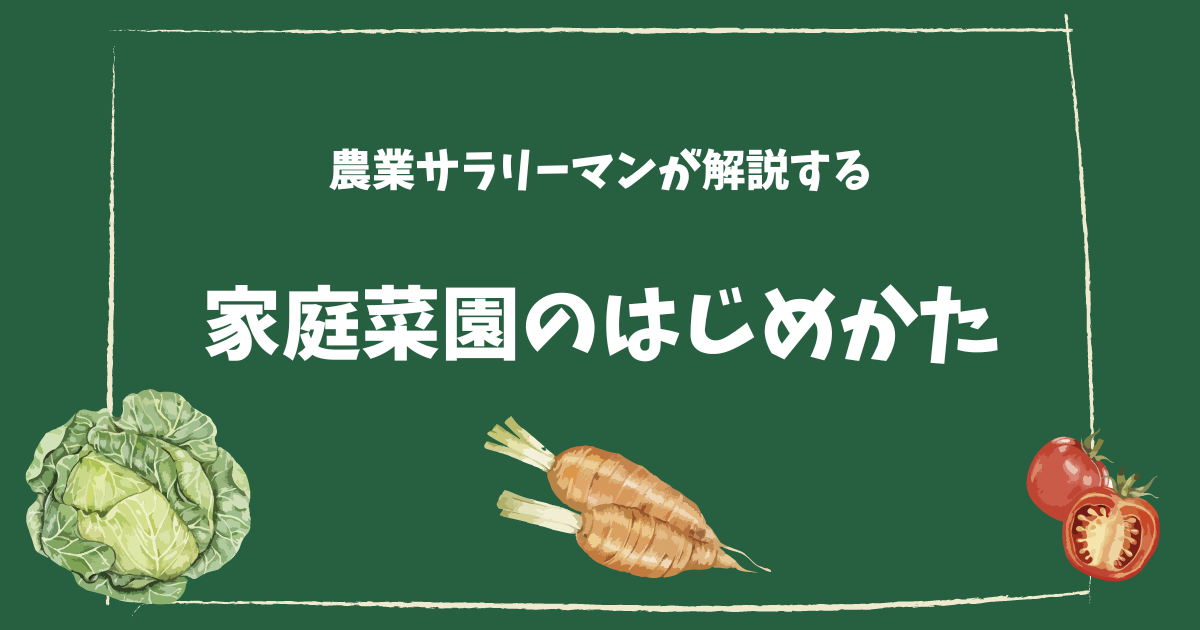




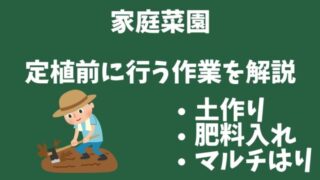
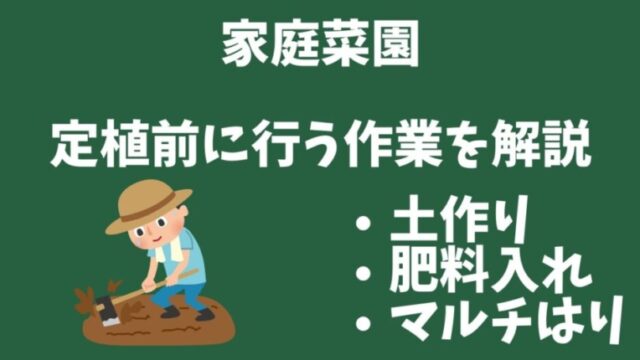

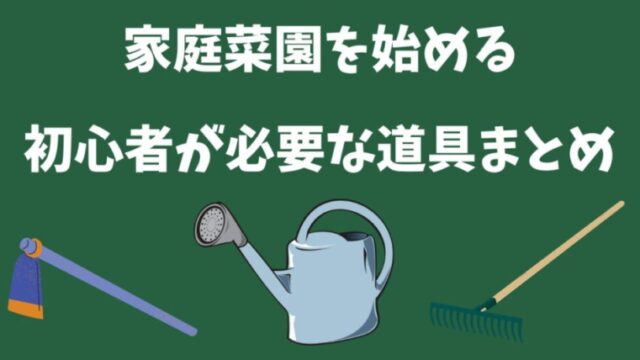


スプレータイプで使いやすい農薬があるので、抵抗感が無ければ使ったほうが病、虫害を抑えられます。厳しく安全性試験がされているので用法、用量を守れば問題ないですよ。